
岐阜の二次試験。
こんにちは、Kaiです。世間が参議院選挙で盛り上がるなか、岐阜県の教員採用試験を受けてきました〜。
僕は愛知での教員経験があるので二次試験からの参戦。さて、今回はどんな問題が出て、どんな解答をしたかを紹介します。試験内容は小論文と実技。詳しくは以下のとおりでした。
1.小論文
2.実技
-1.個人面接
-2.プレゼン面接
-3.模擬授業
今回は小論文について振り返ります。対策の一助にもなれば幸いです。
小論文のテーマと解答
テーマ:変化の激しい社会において、教員が主体的に学び続ける「新たな教師の学びの姿」が重要視されている。教員が「主体的に学び続ける姿」を児童生徒に示すことにはどのような意味があると考えるか。あなたが目指す教員像を踏まえて、具体的に述べなさい。(1時間、720〜800字)
答案:
私の目指す教員像は「常に学び続ける教員」である。教員が主体的に学び続ける姿を生徒に示すことの意味は、生徒の自立力、共生力、創造力の向上につながるということである。高等学校を想定し、成人を迎える生徒にとって教員が最も身近な大人である点を踏まえ、その意義について論じたい。
変化の激しい社会は教育へも大きな影響を及ぼしている。ICT技術の進展、変わりゆく大学入試制度、生徒指導から支援へとさまざまである。そうした社会のニーズに前向きに応えるために、教員は常に学ぶことが必要である。例えば英語の授業でICTを活用する際にSAMRモデルの実践が挙げられる。これはICTの活用を代替、拡張、変容、再定義の四段階に分類する枠組みである。再定義にいくほど活動が高度となるが、これを把握した上でICTを活用することで目的を明確にした授業を展開できるようになる。そこで生まれる疑問や課題は、単にICT技術を取り入れるよりも高度なものとなることが多く、教員にとっての新たな学びへとつながる。そして、同僚性を生かし学校としての協働的な学びへ昇華させることも可能である。このような教員の前向きな学びの姿勢は生徒の学ぶ姿勢へ良い影響を与えるだろう。岐阜県の掲げる自立力、共生力、創造力をどのように培っていくのかにおける実践例としての役割を果たしているからである。教員は生徒にとって支援者であるとともに、具体的なロールモデルの一例でもあるため常に学び続けることがより大切なのである。
社会は大きく変わってきたとともに今後も変化していく。そこでは一段と主体的に学び、人とつながり、自分を高めていく力が重要となる。だからこそ、生徒がその素養や資質を高めるためにも教員が常に学び続ける姿を示すことには教育的に大きな意義があると考える。
分析用
私の目指す教員像は「常に学び続ける教員」である。教員が主体的に学び続ける姿を生徒に示すことの意味は、生徒の自立力、共生力、創造力の向上につながるということである。高等学校を想定し、成人を迎える生徒にとって教員が最も身近な大人である点を踏まえ、その意義について論じたい。
変化の激しい社会は教育へも大きな影響を及ぼしている。ICT技術の進展、変わりゆく大学入試制度、生徒指導から支援へとさまざまである。そうした社会のニーズに前向きに応えるために、教員は常に学ぶことが必要である。例えば英語の授業でICTを活用する際にSAMRモデルの実践が挙げられる。これはICTの活用を代替、拡張、変容、再定義の四段階に分類する枠組みである。再定義にいくほど活動が高度となるが、これを把握した上でICTを活用することで目的を明確にした授業を展開できるようになる。そこで生まれる疑問や課題は、単にICT技術を取り入れるよりも高度なものとなることが多く、教員にとっての新たな学びへとつながる。そして、同僚性を生かし学校としての協働的な学びへ昇華させることも可能である。このような教員の前向きな学びの姿勢は生徒の学ぶ姿勢へ良い影響を与えるだろう。岐阜県の掲げる自立力、共生力、創造力をどのように培っていくのかにおける実践例としての役割を果たしているからである。教員は生徒にとって支援者であるとともに、具体的なロールモデルの一例でもあるため常に学び続けることがより大切なのである。
社会は大きく変わってきたとともに今後も変化していく。そこでは一段と主体的に学び、人とつながり、自分を高めていく力が重要となる。だからこそ、生徒がその素養や資質を高めるためにも教員が常に学び続ける姿を示すことには教育的に大きな意義があると考える。
試験では最後の行まで使ったので、実際の答案はもう少し加筆されますが概ね内容は上記のとおり。では自己分析していきたいと思います。
テーマの読み取りと課題への適合度
課題論文なので、課題に正確・忠実に答えることが求められます。
主題:教員が「主体的に学び続ける姿」を児童生徒に示す意味
条件:①目指す教員像を明確にする、②具体的に述べる
前提:激動の社会だからこそ、教員の主体的な学びが重要となっている
主題:教員が「主体的に学び続ける姿」を児童生徒に示す意味
”生徒の自立力、共生力、創造力の向上につながること”
”そこでは一段と主体的に学び、人とつながり、自分を高めていく力が重要となる”
解答は一応、主題に答えられていると思います。自立力、共生力、創造力は岐阜県が育てたい力として明示しているものですが、それを用語だけでなく内容も理解していることを最終段落でパラフレーズして表現しています。
”実践例としての役割を果たしているからである。教員は生徒にとって支援者であるとともに、具体的なロールモデルの一例でもある”
学ぶ姿勢を見せることが、それらの力を高めるためにどう影響するのかを集約しています。個人的にはもう少し展開すべきだったと思います。ロールモデルになって、何?という感じ。
学んでいるからこそ自信を持って教員は授業をできる、その自信が生徒に伝わる、それは彼らの学ぶ意欲を喚起することにつながり、勉強をはじめ卒業後の諸活動でも生きてくるだろう。
みたいなことを書けばよかった・・・後の祭りですな。
条件①:目指す教員像
”私の目指す教員像は「常に学び続ける教員」である。”
第1文で明記しています。その姿が何を指すかは本論で具体的に展開しています。
今回ありがたかったのは、自分の目指す教員像が課題文の前提となっていたことでした。その課題に沿って展開すること自体が教員像を踏まえています。
ただその後の「意味は〜ということである」という言い回しに表現上の違和感があります。もう少し違う言い回しができたかもしれませんが、課題への明確な解答と読み手がわかるよう課題文の引用にこだわってしまいました。
条件②:具体性と事例の深掘り
高等学校の想定、教員の主体的な学びが意義をもつ一例(英語の授業でのSAMRモデル)
具体的と言えると思います。課題が児童生徒と書いてあり幅が広いため、論じる内容がどの学年層を想定しているかを明記しています。そして、例として学んだ実利とその波及効果を展開しています。
SAMRモデルについては、それ自体を詳しく説明してはいませんが、知らない読者にも「ICT活用の段階的深化を通じて、学びが変化する」という流れができるだけ読み取れるよう記述しました。
懸念点は、高等学校でなくても書ける内容だということ。大学の入試制度に関する知識のアップデートとは違い、どの学年層にも言えることです。最も身近な大人と論じていますが、カバーできていません。これはミスったかもしれん・・・
構想時は、多様化する大学入試へのキャッチアップでもいいかと考えましたが、それだと学ぶ姿を生徒に示すというより学んだ内容が生徒のためになるという論点になってしまうと判断し、やめました。冷静になればそっちで展開できたかも・・・
前提:社会的な前提への対応力
”変化の激しい社会は教育へも大きな影響を及ぼしている”
”社会は大きく変わってきたとともに今後も変化していく”
本論では前提である社会が教育業界へも影響を与えていることを一般導入として言及、結論では現在までの変化と、未来の更なる変化へ言及しています。
その枠組みを逸脱してはおらず、一貫性は保てていると言えるのではないでしょうか。
その他の構成・表現技術について
構成
構成(序論ー本論ー結論)は満たしています。気になるのは本論に導入を入れている点。必要最低限でとどめてるので決してダメなわけではないと思いますが・・・。ただ、これについては言い分があります。
800字という制限から序論を120字程度に収めようとすると、一般的な導入を挟む余地がなかったのです。少なくとも僕の能力では難しかったのです。
内容
SAMRモデルなどのICTを活用し始めてからの学習モデルは、まさに学び続けなければ書けない内容であり、それを言及すること自体が学び続けることの大切さに説得力を与えていると言って差し支えないと思います。
また、多様化する入試制度や、生徒指導が生徒支援となりつつある現場の流れに触れることで、視点が机上の空論でないことを表現しており、現場の変化に対しアンテナを張っていることを示唆しています。
その他
同僚性などのホットワードを割と自然に組み込めたと思います。ただそれを踏まえた学校としての協働的な学びは話が非常に浅いと改めて感じました。自然に話題にはしているものの、とってつけた感があります。
構成に10分、書くのに40分、見直しに10分。一応しっかり見直せたと自覚しています。その上で、目立つ誤字脱字はありませんでした。文末が単調だったので、表現はもう少し工夫できたなーというのが本音です。
最後に
いかがでしたか。今回は小論文を誇張抜き・謙遜抜きで自己分析してみました。意図をふんだんに書いた理由は、来年受けることになったときに活用するためです笑。なので、ちょっと自分に甘くない?と感じた方もみえるかもしれませんが、ご容赦ください:)
個人的には、なんとか意図して書ききれたかな〜というところです。極論、小論文を書くだけなら書けます。ただ試験という属性を考慮すると、自分の知識や経験、そして価値観をいかに自然に散りばめられるかが大切ではないでしょうか。
節々にその片鱗をーーーでも決して嫌味なくーーー書くことが、一応できたのかなぁと。どういう採点をされるかはわかりませんが、楽しみです。これで点数めちゃ低かったらどうしよう、と一抹の不安はありますが結果が出たらまた紹介します笑。
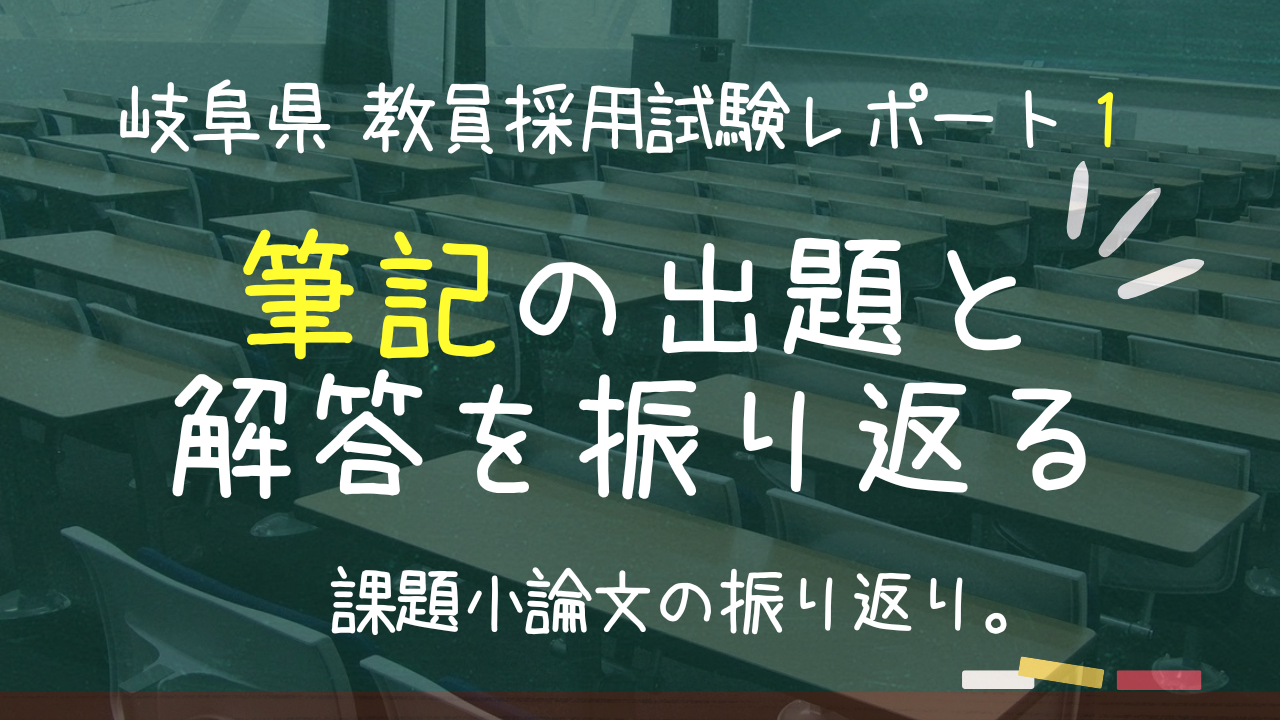

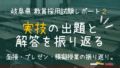
コメント