ども、Kaiです。
前回は小論文の心得として、戦略面をお伝えしました。
今回は戦術編です。戦略と何が違うのか、そう感じる方も少なくないと思いますので、ぜひ読んでみてください:)
戦術【実際に練習する】
戦略が設計図とすれば戦術はさしずめ施工です。実際に取り組むことで小論文の質を上げていきます。そこで僕が意識した次の4つを紹介します。
・下準備
・課題を的確に読み取る
・継続的に書く
・やりっぱなしにしない
1. 下準備
始める前の下準備として、自分の所属先が求めているものは把握しておきましょう。僕の場合であれば、県の目指す人間像や教育目標などです。それらをさりげなく言及できるようにしておくのがポイント。
そして、そうした情報を「私はわかってますからね〜(ドヤっ)」とゴリ押しするのはオススメしません。それは出発点であり、その解像度が低いと途端に内容が薄っぺらくなってしまうためです。
入試のアドミッションポリシーなども同様。そのポリシーをどう咀嚼しているかに価値があるのです。それを掘り下げず、ただ「〇〇な人材に共感した」というだけでは話を展開できません。
2. 課題を的確に読み取る
実はこれが最初にして本質。多くの方が見落としやすい工程です。これは特に、知識が豊富だと思っている方こそ気をつけなければなりません。
なぜかと言うと、問いと微妙にずれた内容を展開してしまうからです。森を知っている人は木を見落としがち。そして、得てして課題文には ― 無意識に読めば ― 問いを見誤るようさまざまな情報が散りばめられています。
問いを的確に読み取り、的確に答えましょう。そのコツは、ズバリ文章を分解することです。情報単位に分け、その優劣や修飾を確認します。
センターピンか、補足的な情報かを把握。そして問いへの明確な答えに補足情報を肉付けしていくのです。
3. 継続的に書く
当たり前ですが一朝一夕に身に付く力ではありません。無理ない範囲で続けましょう。
僕は試験の1ヶ月半ほど前から1週間に1題(書き直しで計2回書く)ペースで取り組み、ラスト1週間は追い込みで3題くらい書きました。
継続的に量をこなすと次のようなメリットがあります。
・書くのが速くなる
・だんだん自分にとって適切な時間配分が見えてくる
・大まかな自分のパターンができてくる
・限られた字数に詰め込める情報はどのくらいかが掴めてくる
言うまでもなく書くのが速くなります。これが時間を捻出する上では決定的な役割を果たします。また、時間配分の微調整を重ねることで、その精度が練り上げられていきます。
それに伴い、自分が取り組む大まかな流れも完成するはずです。取り組み方のパターン化は、考える内容に無駄がなくなる強みがあります。脳のリソースを適所に割くことができるため、より質の高い文章を目指せる、ということです。
そして、書き続けることで戦略の分量配分で身につけたかった「限られた字数にどれだけ核心を詰め込めるか」という感覚を鍛えることができます。
僕は実際に書くと、800字の中の本論では、3つ以上の話を展開すると内容が表層的となり説得力に欠けることを理解しました。盛り込める副題が2つまでと決まれば、割ける字数からどこまで話を深化させるかが決まります。
このように継続的な練習を通し、いわゆる実践的な経験値を身に付けるのがポイントです。
4. やりっぱなしにしない
やりっぱなしは絶対に伸びません。ということで僕は基本同じ設問に2回取り組んでいました。流れとしては、
まず時間内に書いてみる → AIに添削してもらう → もう一度書く
こんな感じです。特に目新しいわけでもありませんが、意識したのは採点基準、プロンプトを明確に入力した点です。
100点満点で以下の小論文の解答を評価してください。
========================
条件 :小論文、720字以上800字以内
補足知識:①岐阜県の目指す人間像…〇〇〇〇〇 ②岐阜県の教育目標…〇〇〇〇〇
========================
テーマ :〇〇についてのあなたの考えを書きなさい。
答案1 :・・・・・
これをテンプレとして使っていました。メリットはいつも同じ観点で添削してくれること。これによりある程度、一貫性の取れた評価を知ることができます。
ちなみに僕が使っていたAIはチャッピーことChat GPTですが、正直なんでもいいです。不安なら天秤AIなどを活用し複数のAIからフィードバックをもらうのも手。AIの性能にこだわること以上に、一貫した採点基準を保つことが大切なのです。
最後に
量がやがて質となる、これは間違いないと思います。最初から効率ばかりを求めても力は付きません。一方でその量の投下先を見誤ると、やはり思うように鍛わらないでしょう。
テクニックや表現集ではなく、あくまで心得としたのは第一に考えるべき基本だからです。巧みに表現を工夫するのも大切ですが、今一度、大枠である戦略と戦術を見直してみてはいかがでしょうか:)では。
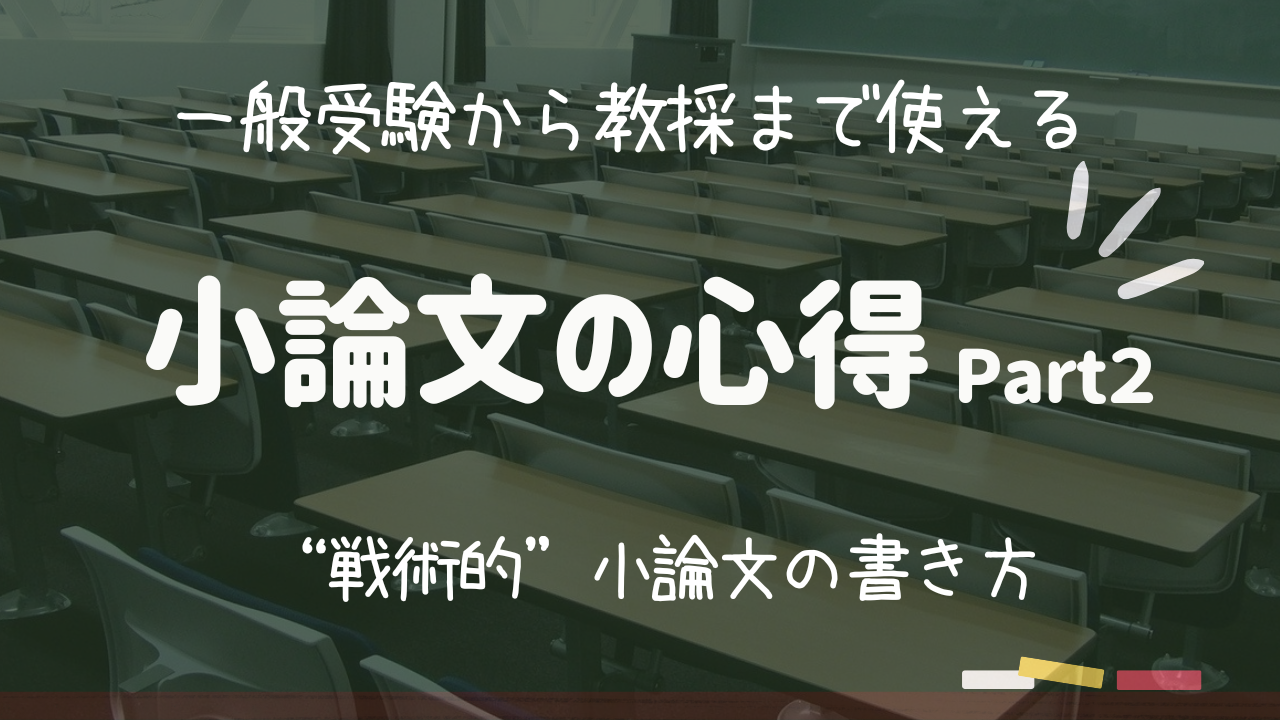
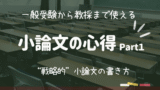
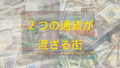
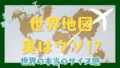
コメント