ども、Kaiです。秋の声が夜を縁取る今日この頃。僕としても感動の学校祭が終わり、平常が帰ってきました。
さて、教員採用試験でも扱った小論文。入試や転職などで見かけることも多く、対策に困っている方も少なくないのではないでしょうか。
そこで、「戦略」と「戦術」という視点で小論文の心得を紹介します。今回は戦略編です。対策の参考となれば幸いです。
戦略【前提を確立する】
小論文の枠組みを把握、すなわち戦略を練りましょう。
・タスクの把握
・時間配分
・分量配分
1. タスクの把握
まずは、小論文のタイプを理解しましょう。課題型の論述なのか、意見型の論述なのか。目的や方向性を決めるための第一歩です。
フランス料理を求められているのに3つ星の中華料理を出してもしょうがないですよね。小論文も同じで、ここを誤ると、どれだけ優れたものでも評価対象外となってしまいます。
今回の教採でいえば、状況がある程度示された意見文でした。
テーマ:変化の激しい社会において、教員が主体的に学び続ける「新たな教師の学びの姿」が重要視されている。教員が「主体的に学び続ける姿」を児童生徒に示すことにはどのような意味があると考えるか。あなたが目指す教員像を踏まえて、具体的に述べなさい。
2. 時間配分
次に解答の時間配分を考えます。2つの要素から概算していきましょう。
1つ目の要素は字数です。何字以内なのか、何字程度なのか、どのくらい書けば良いのかを理解する必要があります。以内であれば9割、程度であれば前後10%で収めるのが一般的です。
2つ目の要素は時間です。何分あるのかを確認します。小論文を書く際は
①構成
②文章化
③見直し
この3ステップに分けられます。文字数と時間から各ステップの時間配分をある程度決めておきましょう。字数と時間次第で、その配分が変わるためです。ちなみに教採の問題は60分で800字以内。僕の場合、
構成 ・・・10分
文章化・・・40〜45分
見直し・・・5〜10分
でした。構成が得意であれば文章を書く時間を増やせますし、執筆に自信があれば構成の時間を増やせます。このように配分は個人差があるため特に唯一の正解はありませんが、自分の中で大まかな基準を作っておくと良いでしょう。
3. 分量配分
序論・本論・結論のボリュームを設計していきましょう。ここで決めるのは具体的な内容ではなく、全体の何割を各パートに充てるかという基本構造です。
序論は15%、結論は10%、残りが本論というのが基本なので、今回は800字ということを踏まえ
序論・・・120字
本論・・・580字
結論・・・100字
という分配で進めました。オーソドックスな原稿用紙であれば最初の6行が序論、最後の5行が結論、その間が本論です。この割り当てを通して身につけたい感覚が、
・どの程度の情報を盛り込めるか
です。例えば120字というのは意外に短く、不要な情報を入れるとすぐに超えてしまいます。となると、序論を1つのチャンク(塊)として、その分量を感覚的に捉えられるかが構成の明暗を分けることになるのです。
最後に
いかがでしたか。今回は戦略、すなわち小論文の方向性をどう決めていくか、その一例を紹介しました。もしかすると革新的な視点はなかったかもしれません。
しかし、手前味噌ながら、僕は今まで担任や主任として数多くの生徒の文章を添削し、民間転職の小論文指導でも高評価をいただいてきました。そして自身の試験でも合格しています。その上で、やはり大切だと実感したのが今回の要点です。
教員採用試験の小論文はもちろん、入試や転職の小論文に悩む方が少しでも「ちょっと改めて見直してみるか」と思える機会に貢献できていたら幸いです:)次回はより実践的な戦術編。では。
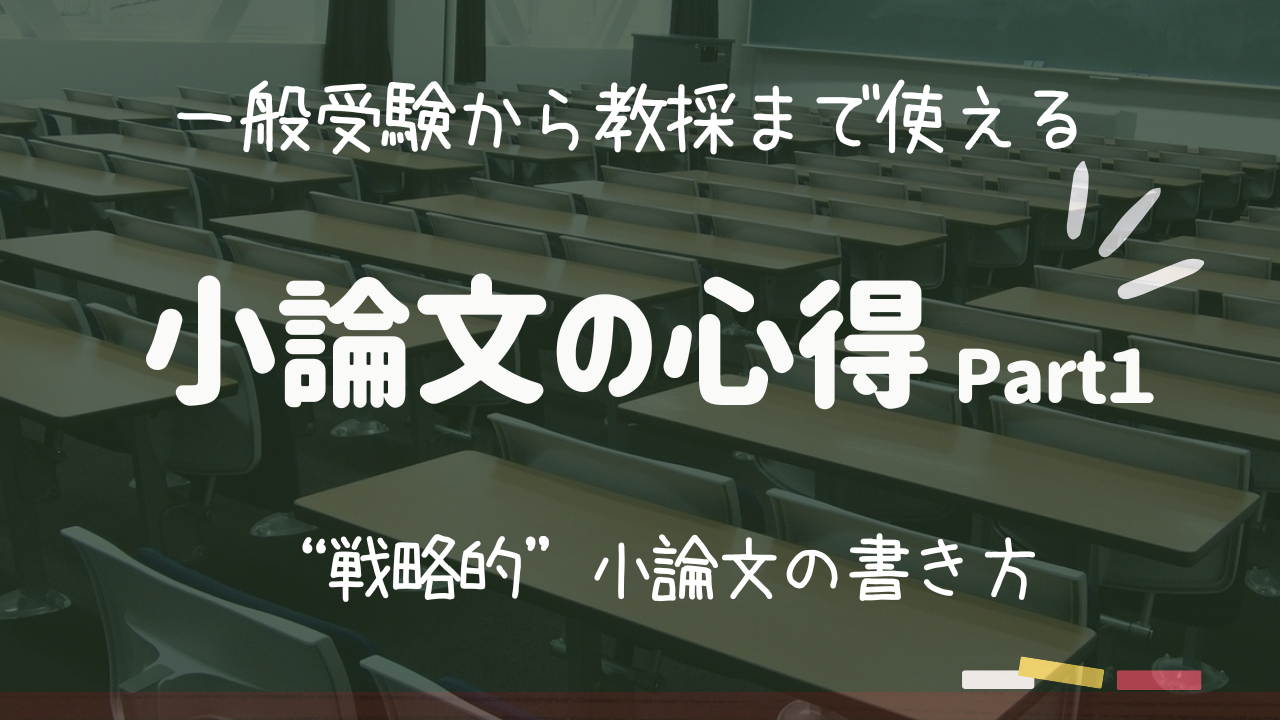
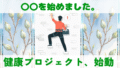
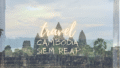
コメント