ども、Kaiです。朝晩寒いのに日中はまだ日差しが暖かい。不思議な時期になりました。さて、前回は最初にして最も大切な”ライティングができる人”を考えました。
今回からはライティング力を決める3つの要素、その1つ目である”英語の表現力”を分析していきます。
では早速みていきましょう。
英語の表現力
文法・語彙など、いわゆる英語の知識。ここでは大きく次の3つの側面に分解して書いていきます。
1.範囲
2.奥行き
3.運用力
その1:知識の範囲
第1に知識の範囲です。英語でいうbreadth(広さ)に該当します。
細かくは単語を知っているか、品詞を知っているか、文構造を知っているか。
その他には、文法事項についてどの程度使えるか。この場合、現在完了形や受動態・関係代名詞などをどの程度知っているのか。
語法も同じです。by the wayで”ところで”だったり、a mistakeにはdoよりmakeが使われるだったり、慣用句やコロケーション(語の相性)をどの程度知っているのか。
構文なども含まれるでしょう。言わば、英語に関する全ての知識です。
その2:知識の奥行き
第2に奥行き。これは表現の幅を指します。
たとえば日本語で”音のない状態”を表す形容詞に”静かな”、”静寂”、”しじま”という言葉があります。このように言葉には同じ意味で違う表現が存在します。
この英語版です。good, fantastic, phenomenalなど、英語も日本語に負けず劣らず多彩な表現に溢れています。この奥行きこそが文章の柔軟性を決める要素です。
同じ意味の単語をたくさん知っておくと、単調な文章を脱却し、的確な描写を捉えるようになるので、読んでいて面白い文章になります。さらに、さまざまな格調に適した文を作成できるのも強みです。
その3:知識の運用力
そして最後は、知っている知識をどの程度“正確かつ適切に”使えるかという力です。英語でいう accuracy(精度)に近い概念ですが、ここでは実際の使いこなしに焦点を当て“運用力”と呼びます。
関係詞や仮定法を知っていても使おうと思うとなかなか正確に使えない、というのは珍しくありません。難しい表現をgoodでぼかしてしまうなどもここに入ります。
また、見落とされがちですが文体の格調もここに入るでしょう。英語ではレジスターと呼ばれます。端的に言えばカジュアルとフォーマル、アカデミックとノンアカデミックの使い分けです。
ここで難しいのがアカデミック vs ノンアカデミック。
例えば大学ではAlsoやIn additionよりMoreoverやFurthermoreが好まれます。これは前者が付け加えとして軽いニュアンスを含むため、論説を前提とする学術ライティングと相性が悪いためです。
しかし、英検のライティングでは模範解答例になる程度にAlsoを使うことができます。これは英検がレジスターの厳密さまでを評価していないためです。
こういった運用力を精度という尺度で捉えることができます。適切な使用ができなければ、知識を知っているだけのインプット達人で終わってしまうため、結果的にライティングの英語レベルを大幅に損ねてしまうのです。
最後に
いかがでしたか。今回は英語の表現力を3つの側面に分類してみました。知識の範囲、奥行き、運用力。そして、これらを統括したものがここで言う英語の表現力です。
このグループ分けは、自分がどんな角度で英語力が足りていないのかを示す指標となります。ライティングができないと漠然と考えている学習者は、まず自分の英語力を把握してみましょう。次回は、この「英語力の基盤」をもとに、ライティングのもう一つの柱「構成力」を掘り下げていきます。
ではまた。

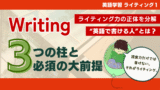
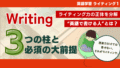

コメント