ども、Kaiです。最近本を読み漁っているのですが、遂に出会いました。ここ最近で1番よかった本です。ということで今回紹介する本は「教育」に関する内容になります。
本のタイトル:教育格差の診断書 データからわかる実態と処方箋
著 :川口俊明
出版社 :岩波書店
本の長さ:238ページ
”思いつきや俗説ではなくデータに基づく実態解明と対策へ”
この1文、なんとも僕が好きそうな言葉を並べています笑。教育は科学だと思っている僕からしたら、この本はドンピシャと言わざるを得ません。この本は教育を“感覚ではなくデータで語る”ための本で、こんな方にお勧めです。
・経験値のみに基づく決定に不満がある
・なるべく客観的に物事を捉えたい
・教育の現状をデータで知りたい
僕がこの本をおすすめしたいポイントは・・・
「なんとなく」を可視化
では早速見ていきましょう!
「なんとなく」を可視化
本書の目次は次のとおり
第1章 日本の教育行政が実施する学力調査の問題点
第2章 学力調査を分析するための基礎知識―朝ご飯は学力に繋がるか?
第3章 進級しても変わらない格差―児童間・学校間における格差の平行推移
第4章 学習時間格差を是正するには―子どもの環境差に応じた働きかけ
第5章 小学生のグリット(やり抜く力)格差の推移
第6章 学校文化と教育格差―日本社会に文化資本概念をどう適用するか
第7章 アンケート調査の落とし穴―客観的な数値データは正しいか
終章 「教育改革やりっ放し」のループを抜け出すために
川口氏を含め、早稲田大学准教授や横浜市立大学教授など6名の有識者が執筆されています。とりわけ僕が刺激を受けたのは第1章と第4章。
資料から得られたとされる情報は「どう分析された考察なのか」を考えなければならない、そんな喚起を促してくれる第1章。データから読み取れる情報と、読み取ったとされる情報は実は食い違い得ることを非常にわかりやすく説明してくれています。
一方で、画一的に説明できそうでできない要因を明らかにする第4章。学習時間の伸長のトリガーは、学力層によって異なる。「点数が上がれば自然と増えるもの」と思っていた僕にはかなり新鮮な話でした。決してそうではないことをデータベースで知り、反省するきっかけとなりました。
本書は「感覚的にはこうだよね」に対する「そうとは限らない」を理路整然と展開しています。“数値”を読むのではなく、“解釈”を問う姿勢に焦点を当てており「そうとは限らない」と思える視点を養える一冊です。
最後に
いかがでしたか。数年前、『FACTFULNESS』という本が話題となり、僕たちの感覚と現実との間にあるギャップをデータで可視化しました。
今回の「教育格差の診断書」は、まさにその教育版とも言える存在です。教育という固定観念に縛られがちな社会に、一石を投じる一冊。
現在は、データだけでなく、「読み解いた結果、こんなことが言えます」という分析まで容易に手に入ります。しかし、その真偽を見抜く力を、果たして我々は備えているでしょうか。
調査者の示すデータに潜む恣意性を読み取る力が求められる時代だからこそ、是非読んでみてはいかがでしょうか。では。
本のタイトル:教育格差の診断書 データからわかる実態と処方箋
著 :川口俊明
出版社 :岩波書店
本の長さ:238ページ
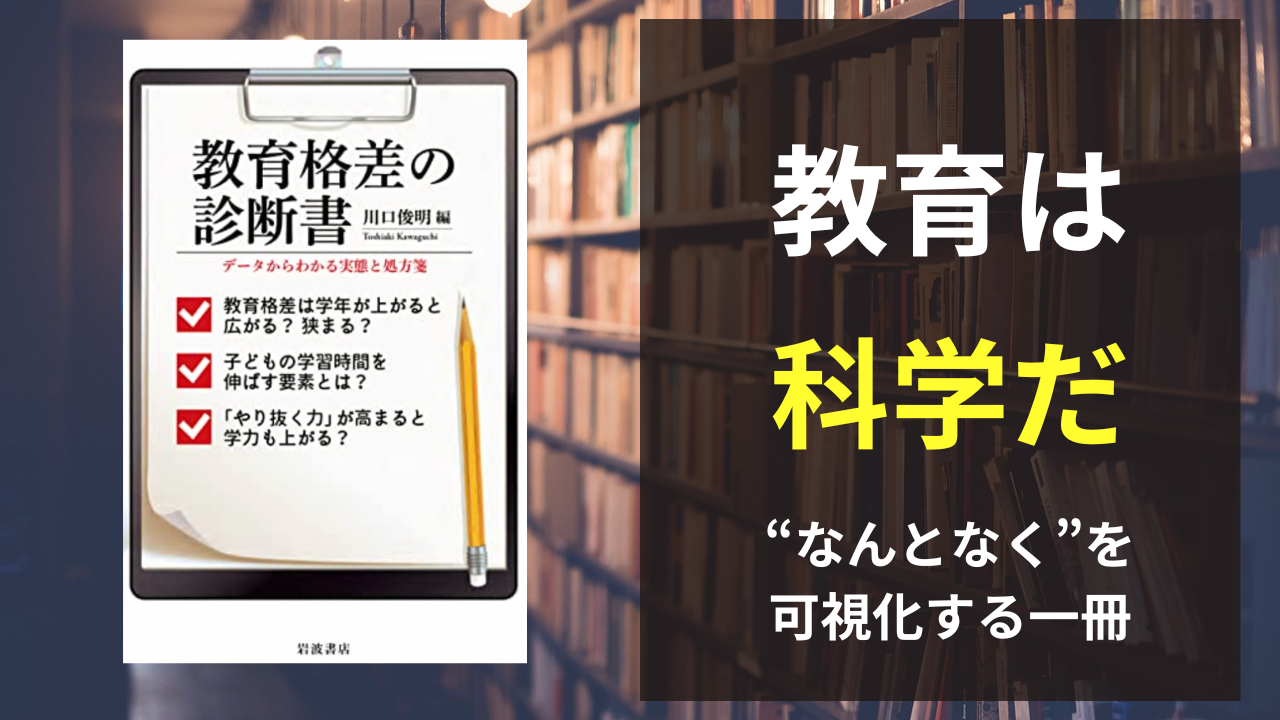
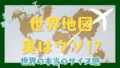
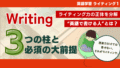
コメント