ども、Kaiです。夏の蒸し蒸しが本格化。エアコンなしには生きられない環境に絶句しています。
さて、今回はウーロンゴン大学で勉強していた時に、本当に読んでおいて良かった文献を紹介します。初めにお伝えしておきますが、これは100%僕の経験に基づく選定です。
僕の教育観がバンバン反映されてますが、もしご興味あれば覗いてみてください:)
1)Brown, D, H. & Abeywickrama, P. (2019). Language Assessment, Principles and Classroom Practices, Third Edition, Ch.3, 57-89
課題テキストです。評価論を包括的に取り扱っている本になります。個人的にはItem FacilityやItem Discriminationといったテストの適合度を測る項目を取り扱っているのが高ポイント。
実際、受験者にとってのテストの難易度を数値化するのは難しいというのが一般論ではないでしょうか。感覚的な要素が多いためですが、それを可能にする公式が存在するというのは理論好きな方にはかなりハマると思います笑。
2)Choi, F. F.-M. (2009). Personal multimedia player for english listening training. Ubiquitous Learning, 1(1), 67–76.
リスニングの実証的文献。台湾という教育事情が似通った環境で、リスニングの具体的な実験をおこなっているため応用がしやすい点で非常に参考になります。
3)Seifert, T. & Bar-Tal, S (2023). Student-teachers’ sense of belonging in collaborative online learning. Education and Information Technologies, 28, 7798-7826.
教職志望学生を対象に、オンライン協働学習における「帰属意識」の形成要因を明らかにした実証研究です。
特に、初期段階での丁寧な技術支援、オンライン学習への適応性、協働学習の経験が重要な要素として示されていて、オンラインラーニングの設計や学習者支援に関する基礎的理解が深まります。
オンラインラーニングの進展により、対面学習とのバランスは今まで以上に重要となっていきます。そこでは感覚や経験だけでなく理論的なアプローチも大切。その点で、とても参考になる文献です。
4)Wang, W., Wang, X., Li, S., Ma, T., Poni Liu, M. N., & Sun, H. (2024). The relationship
between emotional interaction and learning engagement in online collaborative learning: Moderated mediating effect. Psychology in the Schools, 61(4), 1549–1564.
こちらもオンライン学習環境に関する文献。オンライン学習において「感情的なやり取り(共感や励ましなど)」が学習者の心理的孤独感を減少させること、学習への積極的な関与を促進することなどを明らかにしています。
オンラインだからこそデータ的な部分が見られがちですが、感情的な部分も学びには不可欠という事実を展開しているところがおもしろいです。
いかがでしたか。いろいろある文献から僕の中で有用性の高いものをいくつか紹介しました。読んでみて「ちょっと違ったな」は日常茶飯事で、腐るほど読み漁る中で出会うキラッと光る文献。
ちなみにUOWは手続きすれば卒業後も数年は図書館へアクセスできます。方向性がないと探すのは難しいですが、たまに良い文献に出会うと、発掘に似た何とも言えない楽しさを感じます。
他にも興味深い文献があるのですが、今回はここまで。また、英語教育やオンライン学習関連でおもしろい文献があれば是非教えてください:)では。

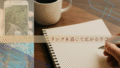
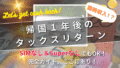
コメント